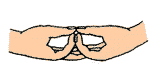九品寺訪問記 2003年8月20日 今回のお寺さんは、”浄土宗・九品寺“ 鎌倉駅東口からバスで7〜8分徒歩では20分ぐらいか、材木座の海岸近くにあるお寺にお伺いしました。梅雨明けしましたよと気象庁が発表してからも雨と低温が続き、残暑らしき日もこれから望めるかという8月下旬でした。 所在地:鎌倉市材木座五丁目13−14 若宮大路から鎌倉消防署を左に入った道路と、小町大路から海岸に向かう道路の角地に位置し道路と山門、山門から本堂とあまり距離がない。山門を入ると、右に「ナニワイバラ」(白い一重のバラ)の棚があり、「ボケ」も植えられていてお花の時期(4月上旬から)はみごとな景色になる。正面に本堂、左に庫裡、本堂裏に墓地がある。 新田義貞鎌倉攻めの本陣跡に、北條方の戦いで亡くなった多くの戦死者を弔うために、 新田義貞が創建したお寺である。 お忙しいご住職に、お時間を頂き庫裡でご説明をお聞きした。 九品寺というお寺の寺号のいわれを伺った。浄土宗三部経のなかに阿弥陀仏が説法され九品來迎印があり(上品・中品・下品にそれぞれ上生・中生・下生があり九品となる)この九品が寺名となっている。又、山号も新田義貞は朝廷の勅を奉じ当地を内裏として陣営を設けたので内裏山になっている。
大切に保管されている当寺三世住職「順妙」が書かれた当寺の縁起書を見せていただいた。内容は、縁起のページに写し書きをしました。 床の間の輪島塗り屏風は法然上人の絵伝(全74ページあり)で、当寺のは6ページ分を日展に何度か入選された方が作製されたとか。平成23年が法然上人800年大遠忌にあたり、「総本山知恩院」に絵伝を所持している寺院より集められ展示されるそうです。
境内から発掘された石像薬師如来像は、当寺建立より古い年代、永仁四年(1296年)に作製されたものだとか。現在は鎌倉国宝館に寄託し展示されている。 又、国宝館には、当寺所有の石像「閻魔王坐像(承応四年)銘」「奪衣婆(だつえば)坐像(承応四年)銘」もあわせ展示されています。
| ||||||||||||||||||||||||