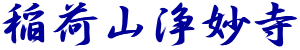

寺の略史当寺は稲荷山浄妙寺と号し、鎌倉五山第五位の寺格を持つ臨済宗建長寺派の古刹である。源頼朝の忠臣で豪勇の士であった足利義兼(1199没)が文治四年(1188)に創建し、初め極楽寺と称した。 開山は退耕行勇律師で、当初は密教系の寺院であったが、建長寺開山蘭溪道隆の弟子月峯了然が住職となってから禅刹に改め、ついで寺名も浄妙寺と称した。 寺名を改称したのは正嘉年間(1257〜59)とみられる。 歴代の住持には約翁徳倹・高峰顕日・竺仙梵僊・天岸慧広など名僧が多い。 中興開基は足利尊氏の父貞氏で、没後当寺に葬られた。至徳三年(1386)足利義満が五山の制を定めた頃は七堂伽藍が完備し、塔頭二十三院を数えたが、火災などのため漸次衰退し、現在は総門・本堂・客殿・庫裡等で伽藍を形成している。 境内は国指定史跡。 開山略伝行勇律師(1163〜1241)は相模国酒匂(小田原市)の人で初名は玄信、荘厳房と称した。幼くして薙髪出家し、真言密教を学んだ。養和元年(1181)には鶴岡八幡宮寺の供僧となり、ついで永福寺・大慈寺の別当にも任じ、文治四年(1188)足利義兼が当山を建立すると開山に迎えられた。 正治元年(1199)栄西が鎌倉に下向すると、その門に入って臨済禅を修め、栄西没後は壽福寺二世に任じている。 頼朝や政子に信任されて戒を授ける一方、「所住の寺、海衆満堂」といわれるほど信望され、実朝もあつく帰依した。仁治二年七月、東勝寺で没した。
浄妙寺訪問記 浄妙寺写真集 
|