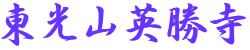
|
寺のある場所は太田道灌 (15世紀中頃) の屋敷跡といわれます。 道灌は幼少から建長寺などで学んだといわれ、江戸城を作り、文武両道にすぐれた武将でした。 英勝寺は1636年(寛永十三年)に英勝院により創建されたとみられます。 英勝院は道灌から続いた太田家の四代目の康資(やすすけ)の娘といわれます。幼名はお八、のち徳川家康(1542-1616)に仕えたときはお梶といいました。 関東を治めることになった家康は1590年(天正十八年)に江戸城に入ってから関東の名門の子孫を江戸に呼び集めましたが、太田家もその中にありました。 あいにくお八の兄の重正が京都にあって不在のため、妹のお八が出向いたのがそもそもの縁といわれています。 お梶は家康に仕えましたが、その信頼は絶大であったといわれております。お梶は関ケ原の戦(1600年)に女ながらもお供をしたと伝えられています。この戦いに勝った家康はお梶の参陣を褒め、戦勝にちなんでお勝という名を与えました。 お勝の局は家康の女子を生みますが早世してしまいましたので、のちに水戸徳川家の祖となる徳川頼房 (1603-61)の養母になります。ここから、後にお勝の局が出家して建立した英勝寺と水戸徳川家の関係ができることになるのです。江戸城内では、お勝の方は、お万の方、阿茶の方などとともに重きをなしました。 家康の死後お勝の方は出家し、英勝院と名乗り、1634年(寛永十一年)徳川家光 (1604-51) から祖先の太田道灌の屋敷があったとされるこの地を賜ることになります。 英勝院はお寺を創建し、水戸徳川家の頼房の娘小良姫(さらひめ)を玉峯清因(清因尼)と名づけ開山に迎えました。棟札によると仏殿は1636年(寛永十三年)にできています。英勝院は1642年(寛永十九年)に65歳でなくなりました。翌年には頼房自身により仏殿が改築され、さらには唐門、祠堂、鐘楼などが造立され、また山門は頼房の子、高松藩主松平頼重により建てられました。英勝院の一周忌には頼房、その子の光圀、頼重らがここを訪れたこともあり、また、本尊の阿弥陀三尊像は、英勝院が将軍就任に貢献したといわれる三代将軍家光の寄進によるものです。 以来、お寺は広大な寺領と住職が代々水戸家の姫君を迎えたことで、「水戸様の御殿」とか「水戸様の尼寺」と呼ばれ、江戸時代には栄えました。 公開されていませんが、裏手の墓地には開山はじめ歴代の住職のお墓(無縫塔、または卵塔といわれる塔)が並んでいます。 第一世は、清因尼(正面に「雄誉」と刻まれています)、以下、清山尼(「松誉」)、清玉尼(「常誉」)、清薫尼(「映誉」)、清月尼(「鮮誉」)、清吟尼(「行誉」)と、同じ様式の大きな塔が寺の格式の高さを示すように並んでいます。 明治になると水戸徳川家の住職もなくなり、関東大震災では山門や仏殿などが倒壊するという被害を受けます。 昭和31年英勝寺文化財復興保存会がつくられ、昭和36年から38年にかけて次々と仏殿、祠堂、鐘楼がなどが修造され、再び昔の姿をとりもどしました。 現在では、江戸初期の貴重な建造物と四季折々の花が咲くことで、多くの方が訪れるお寺となっています。 平成13年には山門復興事業が始まり、柳田法導住職のもと、川崎 肇事務局代表、伊藤玄二郎副代表、内海恒雄事務局長らにより活発な活動が展開されています。 英勝寺訪問記 英勝寺写真集  へ へ |