山門は高松藩主
松平頼重(1622-95)という人によって、英勝院がなくなった翌年の寛永20年(1643)、そのー周忌にあわせて建立されました。
頼重は、
英勝院の養子となった父 水戸徳川家の初代藩主
頼房の 長男です。なぜ山門を寄進したのか、少しさかのぼりましょう。
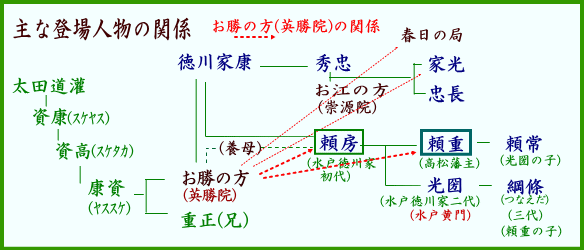
すでに触れましたが、
英勝院は、家康が亡くなったのち出家しますが、
家康の側室で、
お梶、次いで
お勝(
お勝の局)と呼ばれました。
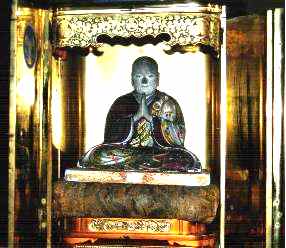
(左: 厨子に入った法体の
英勝院)
慶長八年 (1603)、
家康との間に女の子が生まれました。家康16番目の子で、女の子としては5番目で、
市姫と名づけられました。
ところが3歳で早世してしまいます。 悲しむお勝があまりにも不憫なので、家康は11男の
頼房を
お勝の養子にし、
お勝の局を母親代わりとしました。
頼房は3歳で早くも常陸国下妻10万石、そして慶長14年(1609)には水戸25万石の藩主となりました。そして
20歳のときに長男
頼重 を生みます。
(話は核心に入ります。)
しかし、この時 兄の尾張の
徳川家義直 や、紀伊
徳川家頼宣に嫡子がいなかったため、畏れ多いこととし、
頼重 を亡き者にしようとしました。
(万が一将軍に世継ぎの問題がでたとき、尾張や紀伊にくらべ水戸家は格が低かったので、男子の誕生をはばかったためと言われています。)
始末を命じられたものが哀れと思い、
お勝の局に訴え出ます。
頼重は救われ、京都天龍寺の塔頭慈済院に預けられ、やがて出家するはずでした。
しかし、ここでも
英勝院の働きかけで、将軍
家光に拝謁することが出来たり、寛永16年常陸国下館5万石の藩主となり、寛永19年5月(1642)英勝院の計らいもあって、
高松12万石を与えられることになりました。しかしながら、その年英勝院は病の床につき、8月に亡くなってしまいます。
高松に赴いたばかりの
頼重は、亡くなった時には来ることが出来ず、大変残念に思ったことでしょう。
そして、寛永20年 (1643) 英勝院のー周忌に当たって、父の
頼房によって、仏殿(大幅な改修と思われる)、鐘楼、唐門、祠堂などが建立される中、
頼重は
山門を寄進しました。

