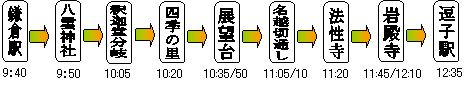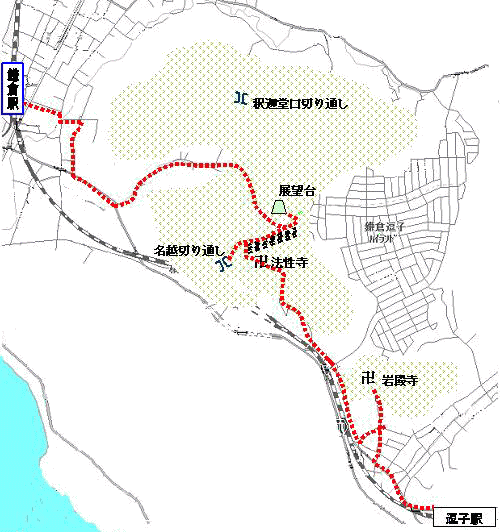|
   |
一番奥の畑の横・看板の近くから笹に隠れるようについている細い道(ちょっと判りにくい)に入ります。人があまり歩いていない荒れた山道を笹を掻き分けながら10分ほど登ると、ハイランドから名越の切通しに通じる尾根道に出ました。 ここから展望台(パノラマ台と案内標識には書いてある)までは5分たらずの登りで、ここからは鎌倉市街から逗子市街が一望できます。今迄休みなしで歩いてきたので展望を楽しみながらゆっくりと休憩しました。一寸曇っているので残念ながら「伊豆の大島や富士山」は見えませんでしたが江ノ島も少し霞んではいましたが良く見えました。 展望をしばし楽しんでから今来た道を引き返し、登って来た道を右手に見て「お猿畠」と言われる山の尾根道を法性寺(ほっしょうじ)に向かいました。この尾根道は「お猿畠の大切岸(おおきりぎし)」として有名な崖の上を通っています。 大切岸は、北条泰時の時代に三浦半島を拠点とする三浦氏の侵入に備えて造られたものと言われている崖で道からその一端を眺めることができます。 鎌倉に長年住んでいながらまだ名越の切通しには来たことが無い、と言うUさんの希望で法性寺への道を通り越して名越の切通しへ行きました。Uさんは初めて来た記念にと駒止めの石など、その大きさに感心しながらカメラに収めていました。 |
名越の切り通しから今来た道を引き返して法性寺への細い急な坂道を下ります、昨日までの雨で濡れて滑りやすいので注意しながら歩きました。一番高い所の墓地から見ると「大切岸の断崖」が一望できます。
法性寺(ほっしょうじ)は、文応元年8月に暴徒が松葉ケ谷の庵を襲い、火をつけて日蓮を殺そうとした時に山王権現の白猿が現れて日蓮を裏山に誘い岩窟に隠して難を逃れさせました。
この岩窟を霊蹟として寺を建て、猿畠山法性寺(えんはくさんほつしょうじ)と称するようになったと伝えられる由緒あるお寺で、松葉ケ谷とは名越の山を隔てた反対側(逗子市)にあります。
久しぶりで来た法性寺は綺麗に整備されて以前のような山奥の雰囲気は無くなっていました。
次に訪れる岩殿寺の階段を考えて少し体力を温存しようと、石段を避けて車の通れる道を下り山門から横須賀線の線路沿いの道に出ます(鎌倉方面を見ると名越トンネルの出口がすぐ近くに見えました)。 しばらく通りを歩いて脇道に入り岩殿寺(がんでんじ)に到着。
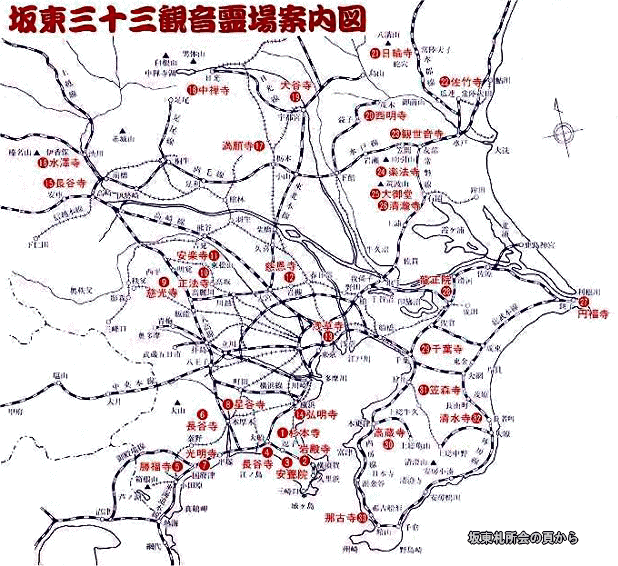
坂東札所会のページに各札所の紹介があります。
|
海雲山岩殿寺(岩殿観音) 曹洞宗 は、次のように紹介されています。 本尊:十一面観世音菩薩 開基:徳道上人・行基菩薩 創立:養老五年(七二一) 徳道・行基両上人の開基 表参道の「写し札所」の観音さまを拝しながら行くと巡礼者としての心構えがおのずから整ってくるのが有難い。山門を経て百余段の石段を踏むと江戸期再建(逗子市重文)の観音堂である。古木に囲まれたここの風致は森厳そのものといえる。 寺伝によれば大和長谷寺の開基徳道上人が、ここで熊野権現の化身である老翁に逢い、霊地たるを知り、また数年のちに僧行基が訪れて十一面観音の石像を安置したのが開創という。本堂裏の石窟に立ち給うご尊像、これに寺号は由来する。全体にはっそりと丸みのあるお姿に生身の菩薩を感じ、合掌せずにはおられない。 岩殿寺のホームページはここから入れます。 |
 |
岩殿寺(がんでんじ)の入口には立派な「岩殿観音寺」と彫られた石柱が立っていました。 「ご詠歌を刻んだ石碑」と「南無観世音菩薩」の赤い旗が並んでいる参道をしばらく行くと突き当たりに山門が見えます。 山門の手前の入口左手に寺の縁起が刻まれた石碑が立っていました。参道から15段ほど石段を登った所に山門があります。 |
 |
山門をくぐり「納経所」の立て札に従って左に入った所のお堂の庭には紅白のシュウメイギクが綺麗に咲いていて見事でした。 寺の紹介記事で 「山門を経て百余段の石段を踏むと江戸期再建(逗子市重文)の観音堂である」 と書かれている石段は、Uさんが数えたところ127段だったとのことです。 |
 |
石段の途中に爪堀地蔵と書かれた風化した2体の石像が祀られていました。 頑張って登り観音堂と堂の裏にある石窟に祀られている観音様をお参りしましたが、石窟の中は暗くて観音様は見えませんでした。 観音堂の横から裏山を一周するよく整備された道があるので、一番高い場所に立っている観音像を拝んで一回りして戻りました。 |
岩殿寺を後にして車の多い通りを避けながら逗子駅に急ぎました。逗子駅に着いたのが12時半過ぎなので、駅近くの店で昼食を取ってから電車で鎌倉駅下車組と大船駅下車組と流れ解散。
第15回のアウトドア同好会も無事に終了しました。