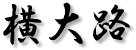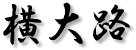|
 源頼朝の父義朝の館跡と
云われている寿福寺付近は、鎌倉と外部の交通の要路であります。この地より北上し、亀ケ谷を越え山之内(北鎌倉)に抜けて大船方面よ
り武蔵府中方面に向う路。海蔵寺方面に進み、仮粧坂を登り梶原村から藤沢方面から京都に通じる路の拠点となっています。 源頼朝の父義朝の館跡と
云われている寿福寺付近は、鎌倉と外部の交通の要路であります。この地より北上し、亀ケ谷を越え山之内(北鎌倉)に抜けて大船方面よ
り武蔵府中方面に向う路。海蔵寺方面に進み、仮粧坂を登り梶原村から藤沢方面から京都に通じる路の拠点となっています。
この交通の要路と思われる寿福寺門前にある勝橋の近くに、庚申塔群と並んで「源氏山」の碑(いしぶみ)があり、そこには次のように書いてあります。
「源氏山は初め武庫山と云う 亀ケ谷の中央にある景勝の地なるを以て又亀谷山とも称せり 源頼義 義家父子 奥州征伐の時 此山に旗
を立たるにより 或は旗立山と名付く 山の麓寿福寺境内付近は 爾来源氏世々の邸宅たりし地なりと云う 源氏山の名称は之に起因せる
か 旗竿を立てしと云う故址は今尚あり 昭和3年3月建之 鎌倉町青年団」
源氏山の名の由来に関し、源頼義と嫡子の義家が、後三年の役に東国に下ったとき、源氏山の山頂に源氏の白旗を立てたことからこの山を
源氏山との名が付いた。この山の麓の寿福寺付近は源氏の屋敷を構えた所縁ある山である。
新編鎌倉志に「この山を或は旗立山、又御旗山とも云う。(鎌倉九代記)に、源氏山と申すは、古へ八幡太郎義家、東国征伐の為に下り給
ひ、鎌倉に打ち入りて、この山に旗を立、終に強賊阿部貞任・宗任を滅ぼし給へば、或は旗立山とも名くとあり。今に旗竿の跡とてあり。
また(採葉抄)には、この山を武庫山とあり。古老の云、武庫山と云は、この山の古き名なりと云う。(以下略)」と源氏山の由来につい
て説明をしています。
この様に亀ケ谷(扇ケ谷)付近は、頼朝が鎌倉に入る以前より源氏と縁が深い所でした。それ故に、頼朝が治承4年(1180)10月6
日に鎌倉に入るや、翌7日には父義朝の亀ケ谷の邸跡を訪れ、ここに館を建てようとしましたところ、地形が狭いことと既に岡崎義実が小
庵を設けて父義朝の供養をしていたので、頼朝は屋敷の建築は別の場所にしたと吾妻鏡に述べています。
「まず鶴岡八幡宮を遥拝たてまつるたまふ。次に故左典厩の亀ケ谷の御旧蹟に監臨下まふ。即ち当所を選んで御所を建てようとしたが、地
形が狭く、また岡崎義実が、義朝を弔うために小庵を建てていたので、幕府の屋敷を建てるのを止めた」(吾妻鏡)と有ります。
寿福寺の前の勝橋を南の巽荒神の方面に進むと、今小路を通りて大町大路へと通じ、更に旧東海道から藤沢をへて京都方面へと連絡してい
ます。
勝橋の前を東に進み、JR横須賀線の扇ケ谷踏切を渡り「鉄ノ井」(くろがねのい)方面へと進みますと、この付近は往時は窟堂(岩屋
堂)と呼ばれていました。吾妻鏡の文治4年(1188)正月1日の条に「大風、佐野太郎基綱が窟堂の下の宅焼けた。火焔が飛んで他の
屋敷に飛び火した。云々」と述べており、この付近は当時も屋敷が多かったことが想像されます。現在は道幅も狭く、JR線路の西側地域
から若宮大路方面に抜けられる数少ない道の1つとなっています。その為か常時は車の往来が激しく、人々は通り抜けるのに大変苦労して
います。鉄の井付近にて、観光客で賑わう現在の小町通りと交差し、ここにて巨福呂坂へ向う道(旧馬場小路)と、幕府の館のある大倉か
ら六浦路へと向う横大路とに接続しています。
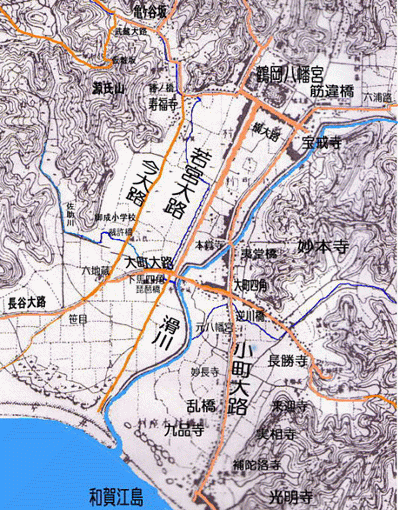 横大路について、鎌倉市
史(総説編)の「小町大路・小坪大路・横大路」項に、次のように述べています。 横大路について、鎌倉市
史(総説編)の「小町大路・小坪大路・横大路」項に、次のように述べています。
「横大路は、(鎌倉攬勝考)に一の鳥居(現在の三の鳥居)の前の東西へ達する道を云うとある。
(吾妻鏡)天福元年(1233)8月18日の条にその名がみえて来るが、建保元年(1213)5月2日の和田合戦を記している条に、
義盛の兵が横大路に到ったところ、御所の西南政所の前で御家人らがこれを支えたとあり、横大路に注して御所南西の道なりとある。赤橋
の前から宝戒寺に突当たる路としてよいであろう。文永3年7月3日の条に政所南大路とあるのもこれである」。
ここにある「吾妻鏡」の天福元年(1233)8月18日の条とは「前浜に死人あり。これ殺害せらるる者なり。泰時は直ちに五余に参
り、評定衆を集めて指示をした。まず御家人等をして武蔵大路・西浜・名越坂・大倉・横大路以下方々の道を固めて、犯人
の捜査するように指示した(以下略)」とあり、同じく健保元年(1213)5月2日の条に「広元朝臣の亭、酒客座にあり。いまだ去ら
ないうちに、義盛が大軍競ひ到りて門前に進む。その名字を知らずといえども、すでに矢を放ちて攻め戦う。その後兇徒横大路(御
所の南西の道)にいたる。御所の南西政所の前において御家人等これを支へ、合戦数反に及ぶなり(以下略)」とあります。
市史の記述の外に、吾妻鏡に横大路の名が見えたのは、元暦2年(1185)5月16日の条に「宗盛父子が鎌倉に入る。若宮大路を経て
横大路に至り云々」、とあります。
次に建久2年(1191)2月4日の条に「頼朝の二所詣の際に横大路を西行、先ず鶴岡八幡宮にご参拝云々」。建久2年(1191)4
月30日「延暦寺の所司2人が鎌倉に訴えたおりに横大路営の南門前を徘徊し、事の由を申している云々」、等の条があります。
横大路の路とは何処から何処までなのかの問いに答えるように、新編相模国風土記稿に「横小路は横大路と称す、鶴岡赤橋より東折して宝
戒寺に到る通衛を云う(以下略)」と、鎌倉市史の説明同様な説明があり、吾妻鏡の記事を見ても御所南西の道とか政所南大路とかと色々
と述べています。
最近発行されました鎌倉国宝館館長三浦勝男氏が編集した「鎌倉の地名由来辞典」(東京堂出版)には、次のように説明しております。
「横大路と称される道筋が徐々に変化し広がりをみせたと考えるべきである。南北朝期の大蔵南小路などは横大路に相当するとみられる。
現況の八幡宮周辺の道筋は、のちの仁治頃北条泰時によって整備されたのが基跡となっているだろう云々」とあります。
このような事から横大路は、鎌倉十井の一つ鉄の井(くろがねのい)の先の旧馬場小路より始まり、この路を東に進み
鶴岡八幡宮太鼓橋前にて若宮大路と交叉し、宝戒寺(ほうかいじ)前にて小町大路と接続している、鎌倉の中心を東西に走る幹線道である
と考えられます。
宝戒寺と東勝寺跡
東勝寺
横大路の東端にて小町大路と交差する路の正面に宝戒寺(ほうかいじ)があります。宝戒寺は東勝寺(とうしょうじ)と共に鎌倉幕府の滅
亡に深い関係がる寺であります。元弘3年(1333)5月に新田義貞が鎌倉攻めにて鎌倉に乱入した際に、北条高時は小町の邸(現在の
宝戒寺)を後にして、祖父累代の墓所である東勝寺にたてこもり、鎌倉幕府創立以来150年もの間、繁栄した鎌倉の街を全て焼くつく
し、北条高時は一族総勢八百七十余人と共に東勝寺にて自刃しました。
その後に足利尊氏が後醍醐天皇の命を受けて、北条高時の邸跡に宝戒寺を建立し北条一族の霊を慰めましたといわれております。 
この東勝寺に付きましては新編鎌倉志に次のように述べております。
「葛西谷(かさいがやつ)は、宝戒寺の境内、川を越えて東南の谷なり、山の下に、古の青龍山東勝寺の旧跡あり。東勝寺は、関東十刹の
内なり。開山は、西勇和尚、退耕行勇の法嗣也と云う。今は寺亡たり。「太平記」に、相模入道殿(北条高時)、千余騎にて、葛西谷に引
篭り給ひければ、諸大将の兵共は、東勝寺に充満たり、是は父祖代々の墳墓の地なれば、ここにて兵共に防矢射させて、心静に自害せん為
なりとあり、又相模入道殿も腹切り給へば、総じて其門葉たる人、二百八十三人、我先にと腹切、屋形に火を放たれば、猛火盛んに燃上が
り、黒煙天を翳たり。後に名字を尋ねれば、此一所にて死する者、総て八百七十余人なり。
嗚呼此日何たる日ぞや、元弘三年五月二十二日と申すに、平家九代の繁昌、一時に滅亡して、源氏多年の?懐、一朝に開くる事を得たり。
云々」とあります。
宝戒寺
宝戒寺に付きましても新編鎌倉志に次のように述べております。
「此処は相模入道平高時(北条高時)が旧宅なり。故に源尊氏、後醍醐天皇へ奏して、高時が為に葛西谷の東勝寺を遷して北条の一族の骸
骨を改め葬り。この寺を建立せり。開山は、法勝寺の長老、五代国師なり。云々」とあります。
|