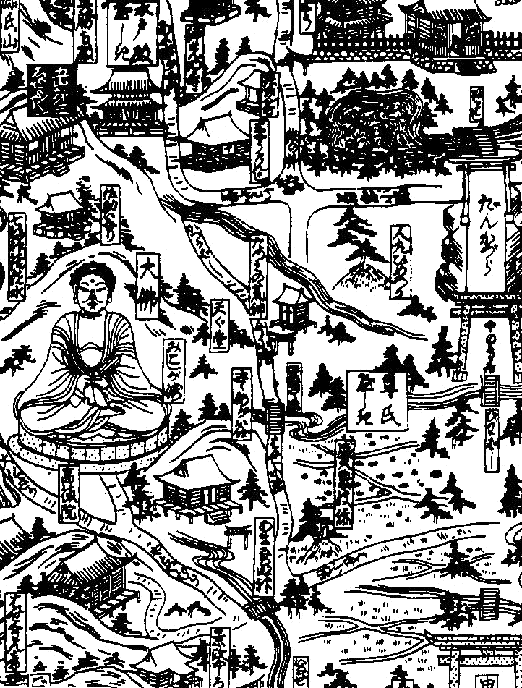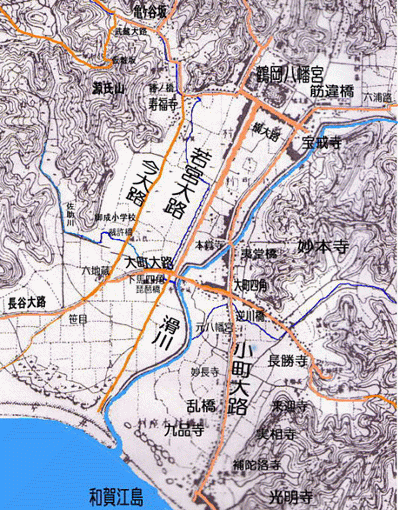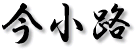
|
今小路(いまこうじ)は今大路(いまおおじ)とも云います。若宮大路の東側に物流の幹線道路小町大路がありますが、
この道路に対応した西側の路は無いのかと考え、鎌倉駅の東口駅前広場に出て辺りを見ますと、左手の赤い鳥居の下を大勢の通行人で賑わう道路があります。
この道は観光客にもよく知られている「小町通」で、若しかしてこの通りが昔からある西の道かと考えました。 そこで、先に紹介した明治15年測量の地図を開いてみると、そこには道はなく畑地と畦道が描いてあるだけで、 とても鎌倉時代から続く道ではありません。
江戸時代の地誌「新編鎌倉志」を調べてみますと、今小路の項に「今小路は、寿福寺の前に石橋あり、勝橋と云う。
鎌倉十橋の一なり。ここより南を今小路と言う。巽荒神の辺より南を長谷までの間は、長谷小路と言うなり」 とあります。
この寿福寺前より東に進み、窟小路を通り八幡宮赤橋前を東西に走る横大路を東進すると、突き当たりに宝戒寺があります。 宝戒寺前にて小町大路に接続し、ここより小町大路を南下しますと小町・大町・材木座を経て相模湾に到達し、 そこには国内は勿論遠くは大陸諸国と交易している和賀江島の港に到着します。 この小町大路を北上し筋違橋にて六浦路にて接続し、荏柄天神から杉本観音寺を経て十二所方面に向かい、 朝比奈切通(あさひなきりどおし)を通り六浦方面へと通じています。更に走水付近より東京湾を横断して房総半島に渡り、 上総より常陸を通り東北方面へと伸びていたと云われている この様に寿福寺付近を中心にして、昔から多くの路が鎌倉の内外部を通じていました。 さらに寿福寺前より今大路を南下し巽荒神の前を通り、問注所の付近に達します。 問注所より裁許橋を渡り更に進みますと六地蔵前に到達します。 六地蔵前よりは大町大路に入り、東に進み下馬を通り名越切通(なごえきりどおし)より三浦方面へ進む道と、 六地蔵より長谷大路に出て笹目の塔の辻より由比ヶ浜方面に進み極楽寺切通(ごくらくじきりどおし)を越えるか、 または稲村ヶ崎を通り京都方面に進む路などがあります。さらに長谷大路を西に進むと長谷観音堂の前に達し、 ここより長谷大仏を経て大仏切通(だいぶつきりどおし)を通り深沢から藤沢へと通じています。 今小路(今大路)に沿って歩く
今小路の付近は扇ケ谷と呼ばれています。しかし吾妻鏡には扇ケ谷の地名は見当たりません。 往時はこの付近は亀ケ谷と呼ばれていました。 吾妻鏡に亀ケ谷の名が最初に出てきますのは「治承4年(1180)10月7日 鎌倉に入った頼朝は 先ず鶴岡八幡宮を遥拝し、 次に義朝の亀ケ谷の御旧跡に君臨する云々」であります。 扇ケ谷の地名については「この辺は全て亀ケ谷と唱え、扇ケ谷は一所の小名なり、されど管領上杉定正ここに住し、 世に扇谷殿と称せられしより亀ケ谷の唱えは漸く廃れ、専ら扇ケ谷と称し習えるなり」(新編相模国風土記稿)とあります様に、 昔は亀ケ谷と云われていたが、今では亀ケ谷の名は 亀ケ谷坂とか寿福寺の山号亀谷山などにその名を残すのみとなりました。 今小路の道を南の方面に向かって歩いてみます。最初は尼寺の英勝寺から案内します。 英勝寺
浄土宗で鎌倉における唯一の尼寺で山号を東光山と称します。 この寺の土地は、元大田道灌の屋敷跡と云われています。道灌の子孫で徳川家康の側室となりましたお勝の局が、 水戸家頼房の義母となりこの地を賜りました。この地に小庵をかまえ、水戸家頼房の娘小良姫を迎え英勝寺を建立しました。(新編相模国風土記稿) お勝の局が寿福寺の前に橋を寄付したことから、この橋を勝橋と云われるようになり、鎌倉十橋の一つであります。 寿福寺
同じく13日の条には「亀ケ谷の地を栄西に寄付せらる」(吾妻鏡)とあります。 その後、政子及び三代将軍実朝はしばしば寿福寺を訪れ栄西の教えを受けたそうです。 また、栄西は宋から帰るときに茶の木を持ち帰り育てていました、 将軍実朝が二日酔いにて苦しんだ際に良薬と称して茶を差し出したそうです。 「健保2年(1214)2月4日将軍二日酔いにて苦しまれ、栄西この事を聞き寺より茶を勧め、 さらに一巻の書を献じた」(吾妻鏡)。この書は「喫茶養生記」と呼ばれ、日本の茶の始祖で、 国重要文化財に指定されています。(講談社学術文庫に全訳書あり) 巽荒神社
巽荒神社から更に南に向かいますと、市役所前の交差点に達します。信号を渡り南に進みますと、 右手に立派な門構えの御成小学校があります。この地は昔の御用邸の跡地で、払い下げを受けて小学校としました。 門に掲げられています門札は高浜虚子の書により彫られた物だそうです。塀にそって進みますと信号のあるT字路に達します、 その角に碑が建っているのが見えます、これが問注所旧跡の碑です。 問注所跡
碑に「元暦元年(1184)源頼朝は大倉幕府の建物の東西の廂を訴訟裁判の場とし、これを問注所と称した。 この問注所に大勢の人々が集まり騒々しい事から、正治元年(1199)に頼家はこの地に問注所を移した、 ここが問注所の遺跡である。」と問注所の由来を説明しています。 碑の、「問注所に大勢の人々が集まり騒々しい事から云々」に関しまして、次のような事件がありました。 「建久3年(1192)11月25日 熊谷直実と伯父の久下直光とが対決し、直実が憤慨に耐えきれず髷を切て逐電した。 この事があってより幕府内での裁判は中止され、その後は名越の三善康信の屋敷内にて行われた。](吾妻鏡) 「正治元年(1199)4月1日問注所を新たに建て、三善義信の屋敷より移転した」(吾妻鏡)とあります。 問注所跡の碑より、御成小学校の塀に沿って進むと、敷地の外れに佐助川が流れています。この川に橋が架かっています、 この橋が裁許橋です。 裁許橋
詳細は鎌 倉十橋を参照してください。 |