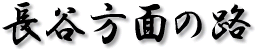
 「新編鎌倉志には今小路として、寿福寺の前から南を云う、巽荒神の辺から南、長谷までの間は長谷小路と云うとあり、鎌倉攬 勝考はこれを踏襲している。(以下略)」。  この六地蔵の角を更に西に進むと、右角に「寸松堂(すんしょうどう)」の建物(鎌倉市の景観重要建築物指定)が建つ「笹目の塔辻」の角に 達する。この笹目の角は「大町大路」の他に、「仮粧坂方面の路」と「長谷方面の路」及び「稲村ヶ崎方面の路」の四本の路の合流点となって いる。 この角地の奥に「塔之辻」の碑があり、そこに「佐々目ケ谷の東南の路の傍二箇所に古き石塔建てり、辻に塔の あるところから塔之辻と言ふらん(以下略) 昭和四年三月 鎌倉町青年団」とあります。 先ず、この角より南西に向う「稲村ヶ崎の路」を歩き、次に現在の由比ヶ浜通に沿った「長谷方面の路」を歩きます。例によって明治15年に 陸軍参謀本部が作成した二万分の一地図を開き、この地図上にて往時の鎌倉の路を想像してみます。 稲村ヶ崎の路 笹目の角にある理髪店脇の小路を進むと、入口は車一台が通れるぐらいの狭い路ですが、先に進むにつれて道幅が広くなり、江ノ電の踏切を渡 り海岸通りを横切りる頃は、幅員が広くなってきます。更に進むと、その先は信号のある交差点により国道134号に接続しています。 海岸線に沿って東西に延びている国道134号に橋が二ケ所架り、橋の下を二条の河が流れています。この河が万葉集にある古名の無瀬川(み なのせかわ)及び歌舞伎の白波五人男が口上を語る、稲瀬川と同名の稲瀬川(いなせがわ)です。橋の少し手前の歩道上に稲瀬川碑が建っていて、次のように書いてあります。 「稲瀬川 万葉に鎌倉の美奈能瀬河とあるは 此の河なり 治承4年10月 政子鎌倉に入らんとして来り 日並の都合より数日の間此の河 辺の民家に逗留せる事あり 頼朝が元暦9年範頼の出陣を見送りたるも 正治元年義朝の遺骨をでむかえたるも共にこの川辺なり 元弘3年 新田義貞が当手の大将大館宗氏のこの川辺に於いて討死せるも人の知る所 細き流れにも之に結ばれる物語少なからざるなり 大正12年3 月 鎌倉町青年団建」 頼朝の政子夫人を初めとして、多くの人々が鎌倉に出入りした稲村ヶ崎の海の路は、昭和の初めに観光道路建設により埋め立ら れ、更に鎌倉の海岸全長に亘り「湘南有料道路」が建設され、その道路が現在の国道134号線となりました。このようにして、古代より多く の人々が歩いたであろう史跡の海の路は完全に無くなり、今となっては「稲村ヶ崎の海の路」は史料によるしか知りようがあり ません。 源頼朝が治承4年(1180)10月6日に鎌倉に入り、一段落したところで妻の政子を呼寄せました。その時の模様を吾妻鏡の治承4年 (1180)10月11日の条に次のようにのべています。「御台所が鎌倉に入られ、大庭景義が政子夫人を迎えました。昨夜伊豆国より到着 しましたが、日並(ひなみ)が悪いので稲瀬川の付近の民家に泊まった云々」とあります。また、この一週間後の10月18日の条には「源頼 朝は、20万騎の精兵を引率して、鎌倉を出発し足柄山を越えて黄瀬河(きせがわ)に到着する。云々」と頼朝が富士川での合戦に向って出発 しています、この時に頼朝の軍勢はどの路を通り黄瀬河に出発したのでしょうか。 ここで問題は、政子夫人が稲村ヶ崎の海の路の何処をどの様にして通って鎌倉に入ったのか、大変に興味があることです。色々と史料を探しま したところ、貞応2年(1223)に書かれた、鎌倉時代の代表的東海道・紀行文の一つ「海道記」(かいどうき:作者には諸説あるが鴨長明 説が有力である)に、次のような素晴しい描写があるので紹介します。  「江ノ島を通過すると、路の北に高い山がある。山の峰は禿げて木々は少なく立派でないが、不思議な姿の石が並んでいて面白さがないわけで はない。立ち止まって石を見ると、昔、波が掘って穴をあけた岩石である。海も長い時間の間に干上がるのかと思われる。腰越という低い山の 間を過ぎると、稲村という所があった。険しい岩が重なり横たわる狭い間を伝わって行くと、岩にあたって打ち上げられる波は、花のように散 り掛ってくる。 ”憂身をば恨みて袖をぬらすともさしてや波に心くだかれん” 申の斜め(さるのななめ)に、由比の浜に着いた。 しばらく休み、ここを見ると、数百艘の舟が綱でつながれ、大津の浦の様子に似ている。 千万の家が軒を並べ、大淀の渡りと変わらない。御霊社(ごりょうしゃ)の鳥居の前で日が暮れた後、若宮大路から、泊まる宿についた。(以 下略)」(小学館 日本古典文学全集より) 稲村ヶ崎の海の路を渡る様子を詳細に描いた「険しい岩が重なり横たわり狭い間を伝わって行くと、岩にあたって打ち上げる波は花のよ うに散り掛る」の描写は、私が子供の頃に良く遊びに行った材木座の和賀江島での遊びを髣髴とさせます。 明治時代に活躍された歴史学者大森金五郎氏の著書「かまくら」(吉川弘文館大正14年発行)に、著者自身が太平記にある新田義貞の鎌倉攻 めの稲村ヶ崎の路を確認したく、数回に亘り渡渉実験を実施した結果を報告しています。 「当時は崖下の水に近いところに通路があったのであろう、、長い年月を経たので風浪怒涛の為に次第に崩壊せられたのであろうか、今は跡形 もない。それ故、元弘3年5月に、新田義貞が大軍を率いてここを渡渉したと云う事は不可能のことではなく、何の不思議も無いことである。 云々」と渡渉実験の感想を述べています。この稲村ヶ崎の通路と似たような路が、昔し鎌倉から小坪の崖下を通り、更に海沿いに大崎の崖下を 通り抜けて徳富蘆花の小説「不如帰」の碑を右手に見ながら、逗子の海岸に達する通路をば子供の頃に良く歩いた記憶があります。 稲村ヶ崎の西側の海浜公園に碑が建っていて、新田義貞鎌倉攻めに就いて書いてあります。「今を距る五百八十四年の昔 元弘三年五月二十一 日 新田義貞此の岬を廻りて鎌倉に進入せんとし 金装の刀を海に投じて 潮を退けんことを海神に祈れりと言うは此の処なり 大 正六年三月建之 鎌倉町青年会 」 小学生の頃の教科書にも見られた、太平記巻十の鎌倉攻めに、新田義貞が黄金の太刀を海中に投じたところ、海の潮が引いたと大潮の様子を述 べています。 御霊神社  海岸の稲瀬川と稲村ヶ崎の中
間にある山裾の近くに、御霊神社(ごりょうじんじゃ)があります。吾妻鏡に始めて御霊神社の名が見えたのは、文治元年(1185)8月
27日の条に「御霊神社が鳴動し、地震のようである。驚いた大庭景能は頼朝に報告したところ早速見にこられた。宝物殿の左右の扉が破損し
ていた。云々」とあります。 海岸の稲瀬川と稲村ヶ崎の中
間にある山裾の近くに、御霊神社(ごりょうじんじゃ)があります。吾妻鏡に始めて御霊神社の名が見えたのは、文治元年(1185)8月
27日の条に「御霊神社が鳴動し、地震のようである。驚いた大庭景能は頼朝に報告したところ早速見にこられた。宝物殿の左右の扉が破損し
ていた。云々」とあります。御霊神社は、当初関東平氏の祖霊を奉祀していたが、後に鎌倉権五郎景政一柱を祀ってます。景政が弱冠16才の時に、源義家に従って後三年 の役(1083〜1087)に参加しました、戦場にて敵の矢を左目に受けたがひるまずに相手を倒し、帰陣して矢を抜こうと三浦平太が景政 の顔に足を掛けたところ、景政は大変に怒ったとの話は有名であります。毎年9月18日に行われる例祭の面掛行列は、神奈川県指定の無形文化財となってます 建久5年(1194)11月21日に御霊神社の前浜にて千番小笠懸(こかさがけ)が行われたと吾妻鏡に述べています。ここで前浜とは坂ノ 下海岸及び由比ヶ浜の海岸を総称し。小笠懸けは、当時は鎌倉武士の間で流鏑馬と共に愛好された騎射の一つで、現在も毎年由比ヶ浜にて年中 行事として「由比小笠懸」行われています。(由比小笠懸) 長谷方面の路 この路は、新編鎌倉志に云う「長谷小路」の一部です。然し、吾妻鏡の何処にも「長谷」(はせ)と呼ぶ地名は見当たりません。吾妻鏡の治承 4年12月20日には、安達盛長の「甘縄」(あまなわ)の家に頼朝が入ったと「甘縄」(あまなわ)の地名が出てきます。その後は、弘長3 年(1263)8月25日に「甘縄に火事があった云々」と火事の記録まで、吾妻鏡には多数の「甘縄」の記録が見られます。この事からも鎌 倉幕府にとって甘縄がいかに重要な所であったかが伺えます。また鎌倉幕府のある大倉と甘縄の間には、頼朝以下幕府の要人が多数往来できる 路が存在していたことは容易に考えられるが、果たしてどの路を通ったかは不明であります。。 安達盛長邸跡 甘縄神明神社の入口に安 達盛長の邸跡の碑があり、そこには次のように書いてあります。 「足立(安達)盛長邸跡 盛長は藤九郎と称す 初め頼朝の蛭が島に在るや 克く力を勠せて其の謀を資く 石橋山の一戦 源家が運の骰 は全く暗澹たる前途を示した 盛長 頼朝に尾し扁舟涛を凌いて安房に逃れ 此処に散兵を集めて挽回を策す 白旗鎌倉に還り天下を風靡する に及び その旧勲に依つて頗る重用せらる 子 弥九郎盛景 孫 秋田城介義景 邸を継ぐ 頼朝以来将軍の来臨屡々あり 此の地即ち其の邸 址なり 大正十五年三月建 鎌倉町青年団」 「徒然草」第184段に書かれた、第五代執権北条時頼の母松下禅尼が自ら障子の破れを張り、節約の戒めを教えたとの、有名な話がある。松 下禅尼が住んでいたのもこの甘縄の館です。 吾妻鏡の宝治元年(1247)6月5日の条に、宝治合戦の時に安達一族の行動した、当時の路の様子が詳細に記録されています。「安達景盛 は一族を引き連れて甘縄の館を出て、門前の小路を東にゆき、若宮大路中下馬橋の北に到りて、鶴岡宮寺の赤橋を打ち渡り、神護寺の門前にお いて時の声を作る。筋違橋の辺に進みて鏑矢(かぶらや)を飛ばす。(以下略)」とあり。ここで云うところの「館の門前の路」が現在の由 比ヶ浜通りに該当するのかは不明ですが、他に適当な路はないので一応現在の由比ガ浜通と推定しても良いであろう。次に若宮大路の中下馬橋 を北に進み赤橋を渡りてとなると、鶴岡八幡宮の現在の太鼓橋の位置にある橋(赤橋)を渡って筋違橋に到る。この橋より戦の合図の鏑矢を 放ったとあります。 何れにしろ、ここに詳しく述べている安達景盛が駆けつけた道筋が、先に幕府要人が甘縄と大倉幕府の間を多数行来した路の一つと考察して良 いのでしょう。 甘縄神明神社  神明社の略誌に次のように述べています。
神明社の略誌に次のように述べています。「和銅3年巳酉(710)に染谷太郎時忠の創建です。永保元年酉年(1081)に源義家が社殿を再建せらる。源頼朝・政子の方・実朝公な ど武家の崇敬が篤く、古来伊勢別宮と尊称せられている、鎌倉で最も古い神社です。社殿の裏山は御輿ケ嶽(見越ケ嶽とも書く)と云い、古く から歌によまれています。 源頼義は相模守として下向の節当宮に祈願し、一子八幡太郎義家が生まれたと伝えられています。 都にははやふきぬらし 鎌倉の御嶽ケ 崎秋の初風 」 吾妻鏡の文治2年(1186)正月2日の条に「頼朝と御台所、甘縄神明宮に御参。帰りに安達九郎盛長に家に入る云々」とあり、その後も 度々参拝しています。 長谷寺 甘縄神明神社から由比ヶ浜通りに戻り、消防署の脇を西に進むと長谷の交差点に到達する、正面に長谷寺がある。その四つ角を右に進むと光則 寺前から大仏殿のある高徳院にいたる路と、大仏切通へと続く路となります。 長谷寺の前を左に進むと御霊神社から極楽寺坂切通を抜け、極楽寺から七里ガ浜を通り江ノ島及び藤沢方面へと通じている。 先に吾妻鏡には長谷の名は見当たらず、甘縄の名称が使用されていると述べました。長谷の名が使用されたのは新編相模国風土記稿に「観音堂 建立ありしより寺号により村名となすなり」と述べている。また、鎌倉市史によれば「現存する史料では文永元年(1293)7月15日の銘 がある新長谷寺の鐘が長谷寺としては一番古いものになるのであろう。長谷の地名がこの寺に由来することは疑いがない」と述べています。ま た長谷寺のホームページに よると「本尊である十一面観音像は養老5年(721)と伝えられていますが、制作年代は未詳と言わざるを得ません」とあります。 高徳院の長谷大仏  長谷寺の前を右に進むと、其
の先には国宝阿弥陀如来坐像の大仏を本尊とする、浄土宗の高徳院(こうとくいん)別名「長谷の大仏様」と呼ばれる寺があります。 長谷寺の前を右に進むと、其
の先には国宝阿弥陀如来坐像の大仏を本尊とする、浄土宗の高徳院(こうとくいん)別名「長谷の大仏様」と呼ばれる寺があります。吾妻鏡の嘉禎4年(1238)3月23日に「今日相模の国深沢里の大仏堂事始めなり。僧淨光、尊卑の多くの人々を勧進させて、この大仏の 造営を計画した。」とあります。現在は深沢と言えば大仏坂の先の旧深沢村のことを指しますが、当時は長谷の大仏付近を深沢と呼んだようで す。 続いて同年の5月18日に「大仏の頭部を挙げた、周りの寸法は周8丈の大きさである」と述べています。その3年後の仁治2年 (1241)3月27日の条に「深沢の大仏殿の上棟をする」と大仏殿の上棟式を行ったとあります。 吾妻鏡とは別に、鎌倉時代の代表的東海道紀行文の一つ東関紀行(とうかんきこう:著作者不明)に、大仏殿の上棟式翌年の仁治3年 (1242)秋に、鎌倉の大仏をお参りした記録があります。 「由比の浦という所に阿弥陀仏の大仏を造営しているとの話を聴いて参拝した。造営の由来を聞くと、定光上人が多くの人々から寄付金を集め てお堂を建てました。お堂は既に三分の二ほど完成していて、大仏の肉髷(にくけい:仏の頭頂を指す)は高く雲に入るようである。白毫 (びゃくごう:額の珠玉)は新しく磨かれて満月のように光輝いている。仏像は早く完成し、もう高く聳えている。奈良の大仏の半分以上にな り、金銅と木像の相違はあるが、尊いことである。」(小学館 日本古典文学全集より)と、ここでは鎌倉の大仏は木像であると説明していま す。 東関紀行の記事の翌年の、吾妻鏡の寛元元年(1243)6月16日に「深沢村に一宇の精舎を建立し、八丈余の阿弥陀の像を安んじ、今日供 養を行う。」と木像の大仏の完成供養を行っている。 更に大仏殿の建立から11年後の吾妻鏡建長4年(1252)8月17日の条に「深沢の里に金銅八丈の釈迦如来の像を鋳始める」との記述が あり。鎌倉の大仏は木像と金銅との2対があるような事になりますが、木製の大仏を原型として鋳型を作り、この鋳型を用い金銅の大仏像を制 作したとも推定されます。 何れにしろ現在の大仏殿の大工事が何年も亘って行われた事から、この付近までは工事用の路が設けられたものと考えられます。さらに大仏殿 の手前から左に分かれた大 仏切通への路もあることから、切通の路を通り現在の旧深沢村から藤沢及び京都方面に通じていたと考えられる。 極楽寺切通の路 長谷寺の前を左に進むと海岸の手前にて右に曲がると、極楽寺切方面に進む。 御霊神社の前を通り星 ノ井から極楽寺切通へと続く。左に極楽寺切通の成就院をみて進むと、極楽寺から針磨橋を渡り、七ヶ浜から藤沢方面へと通じております。 |